乙未のご挨拶
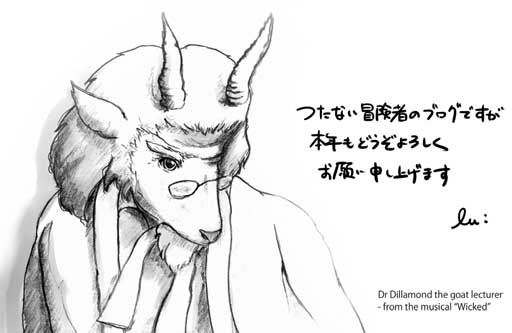
いつものツイートまとめ。今日は、最近ハマっているサプリメントについて書いてみる。
とツイートした通り、最近サプリメントにハマってる。きっかけは、アルバイト先のドラッグストアで売っているイチョウ葉エキスの「頭をよく使う方に」との売り文句。モノは試しとダイソーの安い錠剤を買って飲んでみたら…確かに頭がスッキリしたような気がする!てなわけで、以後ずぶずぶと。
具体的には、抑うつ気分で頭にもやがかかったようだったのが、少し晴れわたり、考えがまとめられるようになったような自覚がある。前回の「りついーと」でも呟いた「食品の機能性評価モデル事業」の結果報告によれば、脳血流改善作用が主な機序らしく、脳機能と脳血流量が相関するとされる脳科学の前提に基づくならば認知機能改善効果があるとしても不思議ではないのかもしれない。
ただ、イチョウ葉は含まれるginkgolic acidが有毒なので、より精製されて安全かつ有効成分も多いLife Enhancementのカプセルに切り替えた…ところ、効果が実感できなくなった。最初の実感がプラセボ効果だったのか、あるいは錠剤の苦味が重要だったのか、経口投与ではなく舌下投与が効いたのか、なんとも判断しかねるところ(まさかとは思うけど、Life Enhancementのほうが品質が悪いという可能性も否定はできない)。うーん…ひとまずこの1ヶ月ボトルを試したあと、より大手どころのLife Extention(以下LEF)の製品を試してみようと思っている。
ちなみに類似というか、より脳血流改善作用が明確なビンポセチンもLife Enhancementのを試してみた。視覚の改善効果が実感しやすいとのことだったのだけれど、私は若干聴覚が鋭敏になったかな?くらいで、あまり自覚的な改善はなかった。念のためこっちもLEFを試す予定(ちなみにビンポセチンは過去に脳血流改善薬として上市されていたけれど、その後効果が確認できず、ホパンテン酸などの他の脳代謝薬とともに回収になった黒歴史がある。健常人なら特に副作用に心配する必要はないと思われるけど、この経緯は知っておく必要アリかと)。
その他のサプリとしては、上の文献ではEPA/DHAも「うつ症状の緩和」に有効かもしれない旨の記載があったので、こちらもLEFの製品を購入してお試し中。イチョウ葉を使っているときに追加したので何ともいえないけれど、今のところ効果の自覚はない。現状使ってるのは、イチョウ葉とEPA/DHAのふたつ。あと、追加でマルチビタミンくらいとってみるかーと、Jarrow Formulaの1-to-3かLEFのTwo-Per-Dayを試す予定。
海外から輸入しているけれど、それでも決して安い買い物ではないし、これ以上は深入りしないように気をつけよっと。特に、いわゆる”スマドラ”は結構怪しいものがあるというか、医薬品や(モノによっては)脱法ドラッグとのボーダーのようなものもあるので気をつけなくてはとは思う(具体的には、例えばピラセタムなんかはメジャーらしいけど、かなり医薬品としての色が濃いように感じるので手出ししないことにした)。でも一方では、上のように使い方次第では本当に保健用に使えるサプリメントもあるようなので、ちょっと上手く付き合えたらいいなと思っているところ。またアップデートあったら、どっかに書いておく。
以下、いつものツイートまとめ。
いつものツイッターまとめ、の前に最近見た、短編アニメーションメモ。
卒業制作のようなのだけど、ストーリーとしても魅力的なのはもちろん、アニメーションというメディアの特性を最大限に活かした作品で凄い。「日本のアニメは萌えばっかりだ」っていう意見があって、私はそれは視野が狭いから気づいてないだけだと思うけれど、一方で前衛的な作品が韓国や台湾からもどんどん出てきていることも事実なので、気に留めておかなくてはならないなと思っている。
他に見たショートフィルム:チルリ
以下、ツイッター振り返り。
いつものツイッターまとめ。試験対策期間に入って暇なので、いろいろ呟いてるみたいだけど、振り返ると特に意義のあるものはなかった(…いつものことか!)
昨年、日本の科学研究で不正件数が少ないのはおかしいという記事が掲載された。井上明久前東北大総長の不正疑惑を中心に、JSTが出資している研究で不正件数がゼロというのはありえないのではないかという記事だった。私も(学内に不正行為で有名になってしまった研究者がいたこともあって)不正ゼロというのはさすがに無いだろうとは思いながらも、同時に、探したところで見つかってせいぜい数件程度だろうと思っていた。「欧米と一緒にするな」というか、この国の科学者の倫理意識は総じて高い水準にあるんだと思っていた。
…甘かったよね。それから一年と経たずに小保方ミサイルが炸裂。さらに悪いことに、その後の理研の後片付けも迷走。井上氏の件もまだ収集がついていないらしい。
単純な剽窃や二重投稿の検出については、ある程度の自動化がなされるだろうと思う。学生レポートではコピペを検出するコピペルナーがあり、5年前に登場してからというもの私の大学の教授も愛用している(らしい。本人が喜々として言っていた)。3年前には、こちらはジャーナリズムにおけるコピペを標的として英国版Churnalismが登場し、昨年には米国版Churnalismが登場した(教えてもらった、米国版についてのthe Atlanticの記事はこちら)。今後、科学論文についてもプレ査読的にこのようなスクリーニングソフトが利用されていくんだろう。
画像についてもSTAP問題以降、編集・加工の形跡を探す試みがますます盛んになった。ついに国内ベンチャーによってLP-examという不正検出ソフトがリリースされ、今後こうしたソフトウェアによるスクリーニングが行われるだろう。
こうした改竄みたいのは自動検出可能なんだけど、しかし、より根深い問題だと思うのは“全てでっち上げ”みたいなものをどうするかということ(例えばES細胞のデータを使ってSTAP細胞のストーリーを創り出す、というような)。こうなってくると巧妙で、シンプルな不正検知での対策は難しいのではないかと思う。過失による不正行為は教育すればどうにかできるけど、悪意があるとなるといかんともしがたいものだし。前にも触れたけど、世の中には相手を邪魔しようと明確な悪意をもって他人の研究を妨害・破壊する輩すらいる。査読つきのNatureですらSTAP論文が載ってしまったというのだから、open journalが流行の御時勢、やってもいない研究結果を報告するような研究者が今後も減るとは考えられない。